|
「あんたがたどこさ」の謎 この歌は、 あんたがたどこさ 肥後さ 肥後どこさ 熊本さ 熊本どこさ せんばさ せんば山にはたぬきが居ってさ それを良士が鉄砲で撃ってさ 煮ってさ 焼いてさ 食ってさ それを木の葉でちょいとかぶせ あんたがたどこさ ひごさ ひごどこさ くまもとさ くまもとどこさ せんばさ せんばやまにはたぬきがをってさ それをりゃうしがてっぱうでうってさ にってさ やいてさ くってさ それをこのはでちょいとかぶせ というものですが、この文字数を数えると90文字となり、9×10文字で蛇行状に表示してみたところ、意味の通りそうな文章を見出しました。 あんたがたどこさひ まくさこどごひさご もとさくまもとどこ やばんせさばんせさ まにはたぬきがをつ しうやりをれそさて がてつぱうでうつて さていやさてつにさ くつてさそれをこの せぶかといよちでは 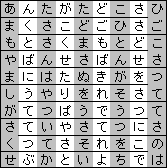 これを左から読んでいきます。 あまもやましがさくせんく とばにうててつぶたささ はやついてかがこくせたり はやさとたどまさぬをうさそい どこもはきれでてれよ こひとがそうつをちささ とせをさつにこで ひごこさつててさのは 天靄増しが作戦苦 鳥羽に討てて瞑た佐々 早着いて加賀国畝田里 早 里 他土増さぬを憂さ素意 何処もは切れ出てれよ 此人が其討つ遠 佐々 歳を察 和手 肥後子察て手然のは 空のもやが増して作戦が苦しくなり 鳥羽で討っていて目を瞑った佐々は 加賀の畝田の里に早くたどり着いた 早くも里では他の土地が増えないことを憂えた思いで どの土地からも最早 はしくれの人が出て行くことを強いられる この人がその討つ以後の佐々 歳を察することができる柔らかい手 肥後の子を察した手のそのような 歌詞に「さ」が多用されているのは「佐々成政」を暗示させるためであると解釈しています。 佐々成政は織田信長に仕えて越前を支配した後、越中富山に移封されます。その成政が越前にいた頃、魚住景固という武将が越前今立郡鳥羽城主でした。この人は朝倉氏に仕えた後、信長に仕え、朝倉氏の家臣に暗殺されます。 魚住景固が暗殺された時に、佐々成政は鳥羽城のあった越前を攻略していて、朝倉氏滅亡後に、成政は前田利家らと共に加賀国に攻め入ります。このことが“うら”の文章の前半に示されていると考えています。実際に、加賀には畝田(うねだ)という地名があり、これを「せた」と音読みすることができます。 その後の文章については、場所が大きく飛躍します。加賀にも肥後にも、「土地が増えないことを憂えて出ていくことを強いられた人物」がいた形跡が認められないので、これを日本全土について言及したものと解釈すると、当時の「文禄・慶長の役(朝鮮出兵)」のことを意味するのではないかと推定しました。 その次は時代が飛躍します。「あんたがたどこさ」の“おもて”の歌詞の「せんばやまにはたぬきがおってさ」とは、川越の仙波東照宮に祭られた徳川家康のことを表わすと考えています。 「猟師(れふし)」を「良士(りゃうし)」と読み替えるのは、家康を悪者扱いするためであると考えています。 その家康を祭ることにこだわったのは徳川家光です。その徳川家光と正室の鷹司孝子が「とおりゃんせ」の“うら”の文章に読み込まれていることに着目します。「討つ以後の佐々」とは、佐々成政当人のことではなく、成政の孫の鷹司孝子のことを表わしていると推定しました。 その次も更に時代が飛躍します。「とおりゃんせ」では鷹司孝子は年増の扱いをされているので、もっと若い肥後の人に着目します。「かごめかごめ」の“うら”の文章で読み解いた本居宣長の弟子に、肥後出身の帆足長秋という人がいました。この人は、本居宣長が『古事記』を注釈した『古事記伝』を、娘の帆足京と共に写本し、肥後に伝えました。その帆足京は三十一歳という若さで亡くなっています。「肥後の子」とは、この帆足京のことを表わしていると推定しました。 --- 「あんたがたどこさ」にみられる「蛇行法則」が何を意味するのかと考えを巡らせ、「蛇行法則」は「惑星の逆行」を表わすのではないかと推察しました。惑星の逆行とは、天空における惑星の見掛け上の位置が、他の恒星に対して逆の方向へ移動しているように見える現象のことです。 この「惑星の逆行」の時期に、歌に表わされた「事象」が起きたのではないかと推察しました。 実際に、魚住景固が暗殺された年代の惑星配置を、Stella Theater Proというプラネタリウムソフトを使って、時代をさかのぼって再現してみました。魚住景固が暗殺されたのは、天正二年正月十四日(西暦1574年2月15日)ですが、それよりも時期の遅い西暦1574年4月10日頃~6月25日頃に、火星がさそり座アンタレスに近づいたあと、逆行していることが判明しました。 冒頭の「空のもやが増して作戦が苦しくなり」とは、悪天候により天空をしっかり読み解けなかったために、暗殺の時期が火星の逆行の時期から逸れたことを表わしていると考えています。 また、「早」という言葉が度々出て来るのは、武将の行動が火星の逆行の時期よりも「早かった」ことを強調するための手法であると考えています。 --- <参考図書> ・ 広辞苑 第五版 岩波書店 1998年 ・ 世界大百科事典 第2版 日立デジタル平凡社 1998年 ・ 佐々成政関係資料集成 編著者:浅野清 新人物往来社 1990年 ・ MapFan.net Version5.5 INCREMENT P CORP 2005年 ・ 福井県文書館ホームページ https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/bunsho/ ・ 天下侍魂 -将を語る- http://1st.geocities.jp/tugami555syou/ (ジオシティーズは2019年3月31日に終了) ・ 【換暦】暦変換ツール https://maechan.net/kanreki/ ・ 歴史読本 細川幽斎と明智光秀 新視点・本能寺の変 新人物往来社 2000年8月号 ・ 本居宣長記念館 http://www.norinagakinenkan.com/ ・ Wikipedia ・ Stella Theater Pro Version3.02 Toxsoft 2010年 ・ Newton キトラ古墳で発見された古代の星図 1998年7月号 --- 戻る |