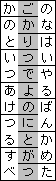|
「かごめかごめ」の謎 この歌は、 籠目籠目 籠の中の鳥はいついつ出やる 夜明けの晩に鶴と亀がすべった 後ろの正面誰 というものですが、この歌詞の中の、最初の「籠目籠目」と最後の「後ろの正面誰」を省いて、 かごのなかのとりはいついつでやる よあけのばんにつるとかめがすべった と「仮名書き」にした33文字の部分を「蛇行状」に表示します。
これを左から縦に読むと、 彼の戸 何時 開けつる術 御家律で予の二十月 の名は イヤル 挽歌めた となります。「めた」は「たくさん」という意味です。これを筆者なりに読み下してみます。 あの戸をいつ開けるかの方法について述べている。 私は士籍剥奪で二十ヶ月の間だけ「イヤル」という名を 名乗っていて、挽歌をたくさんつくった人物である。 --- “おもて”の歌詞の前半にある「籠の中の鳥」は鳳凰の「鳳」という字を表していると考えています。「鳥」という字が「几」という“籠”の中におさまっていることを表していると考えるのです。 日本国内の鳳凰山を地図上で探したところ、山梨県と秋田県の二ヶ所にしかありませんでした。この二点を直線で結ぶと、山形県の「摩耶(まや)山」と「母狩(ほかり)山」の真上を通ることが分かりました。 その摩耶山と母狩山のそばには、出羽三山の「月山」があります。「籠の中の鳥が出やる」とは、この二つの鳳凰山を直線で結ぶことだと考えています。 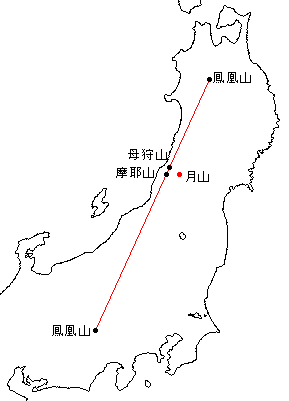 “おもて”の歌詞の後半にある「夜明けの晩」は「日食」のことを表していると考えています。日食が起きる様子を“夜が明けているにもかかわらず晩のように暗い”ことを表していると考えるのです。 次の「鶴と亀がすべった」の「すべる」は「統べる」という意味を表しているという説があります。広辞苑で「鶴亀」を調べると『能の一。唐土の皇帝が春の節会の嘉例として月宮殿で鶴亀の舞を奏でさせ、自らも舞楽を舞う。月宮殿。』とあり、「月」にまつわる宮殿を指してます。 --- “うら”の文章の「彼の戸いつ開けつる術」とは、天照大神が岩戸隠れをしたという「天の岩屋戸神話」を含む「記紀神話」のことを表していると考えています。 また、「イヤル」とは、江戸時代に『古事記伝』を著した「本居宣長(西暦1730~1801年)」を表す「居やる」を示すと考えています。 「御家律」とは、武家の士籍剝奪を意味しますが、宣長が旧姓から武家の血筋である先祖の本居姓に変えたことが、逆の意味で当てはまります。 「二十月」については、その改姓が数え年・23歳の宝暦二年三月(西暦1752年4月)頃から翌年、宝暦三年十一月(西暦1753年12月)に、「香りの良い草、すぐれたもの」を意味する号・芝蘭(しらん)を名乗るまでが「二十ヶ月」となります。 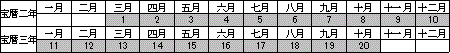 「挽歌」については、天明二年正月(西暦1782年2月)に、師である賀茂真淵の十三回忌追悼歌文集『手向艸』を編んでいることが挙げられます。 <“うら”の文章の別解> かのと いつ あけつる すへ こ かり つて よの にと かつ のなは いやる はか めた 彼の戸 何時 開けつる 術 子 借り 伝 予の 二途 活 の名は イヤル はか めた あの戸をいつ開けるかの方法を、 子を借りて伝える、私の二通りの生きる 名はイヤルのほか、たくさんある。 「私の二通りの生きる名はイヤルのほか、たくさんある」とは、本居宣長が、医者を生業としながら、学者として活動したことを示し、また、彼が青少年期に頻繁に名を変えたことを表すと考えられます。 そして、『古事記伝』の刊行が終了したのは、彼の没後、文政五年(西暦1822年)の事であり、「子を借りて伝える」に合致します。 さらに、この文章の文字数33にも意味があると考えています。暦を概算すると、太陽と月の周期が33年で一巡するのです。月の周期が29.5日で一巡し、29.5日×12=354日で、1太陽年とは11日ずれます。それが積み重なって、11日×33=363日、つまり、33年でほぼ1年分ずれるのです。 「かごめかごめ」には、「暦・天文」にまつわる謎が秘められていると考えています。 --- 「かごめかごめ」にみられる「蛇行法則」が何を意味するのかと考えを巡らせ、「蛇行法則」は「惑星の逆行」を表わすのではないかと推察しました。惑星の逆行とは、天空における惑星の見掛け上の位置が、他の恒星に対して逆の方向へ移動しているように見える現象のことです。 この「惑星の逆行」の時期に、歌に表わされた「事象」が起きたのではないかと推察しました。 実際に、本居宣長が『古事記伝』執筆の準備を始めたのは明和元年(西暦1764年)の事ですが、西暦1764年5月10日頃~7月5日頃(明和元年は6月30日から)に、火星がさそり座で逆行していることが判明しました。 また、『手向艸』を編んだ年の八月に『天文図説』、九月に『真暦考』が成っています。 さらに、「二十月」の終盤に掛かっている、宝暦三年九月二十九日頃~十一月二十一日頃(西暦1753年10月25日頃~12月15日頃)に、火星がおうし座で逆行しています。 この年の八月、『おもひぐさ』という作品の中で煙草への思い入れを示し、かつ、火星を漢名では「螢惑」と言い、五行思想では「火」に配されることから、「煙草」=「火」という図式が考えられ、また、号・芝蘭を名乗る時期とも重なります。 --- <参考図書> ・ 広辞苑 第二版 補訂版 岩波書店 1978年 ・ 広辞苑 第五版 岩波書店 1998年 ・ 世界大百科事典 第2版 日立デジタル平凡社 1998年 ・ 中学校社会科地図 三訂版 帝国書院 1980年 ・ 全日本ロードマップ 国際地学協会 1991年 ・ MapFanIII INCREMENT P CORP 1997年 ・ MapFan.net Version5.5 INCREMENT P CORP 2005年 ・ 本居宣長 人物叢書 新装版 著者:城福勇 吉川弘文館 2005年 ・ Wikipedia ・ 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/ ・ 【換暦】暦変換ツール https://maechan.net/kanreki/ ・ Stella Theater Pro Version3.02 Toxsoft 2010年 --- 戻る |