|
「はないちもんめ」の謎 この歌の種類は全国各地で異なりますが、その中でも比較的単純な京都に伝わる歌を取り上げます。 ふるさともとめて はないちもんめ もんめ もんめ はないちもんめ かってうれしき はないちもんめ まけてくやしき はないちもんめ この文字数を数えると56文字(「ずいずいずっころばし」の112文字の半分)となり、8×7文字で蛇行状に表示してみたところ、意味の通りそうな文章を見出しました。 ふるさともとめて もめんもちいなは んめもんめはない うてつかめんもち れしきはないちも しやくてけまめん きはないちもんめ 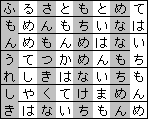 これを右から読んで行きます。 てはいちも めめななもちめといはん いまも もちめめ なけちとも かはて いさも つきくなるめめ てしやはふもんうれしき 手配遅も 米なな餅めと言はん 今も もち米 無けちとも かはて いさも 尽きくなる米 てしゃは不問嬉しき 準備が遅れ 米にしてしまいたい餅ごときと言いたいが 今は もち米もないというけれども そのようなことはない さあどうだろう 尽きてしまう米 文字を書く者は問いただされず嬉しい 「尽きてしまう米」という言葉から、この文章は、米不足により起きた一揆のことを表わしていると解釈します。また、「文字を書く者は問いただされず嬉しい」という言葉から、「言論の自由」を記した明治憲法が発布された明治二十二年(西暦1889年)を基準とした時期に起きた一揆のことを表わすと解釈します。 しかし、その一揆が「どの場所」で起きたことなのかが記されていません。そこで、暗号が織り込まれた他の童歌の解読を参考にします。どの場所でもないなら、幕末の「全国」で起きた「世直し一揆」を表わすと解釈します。この一揆は、開港による輸出の増加や、内戦による米価の高騰をきっかけにして、幕府に対する不満が高じて起きています。 そうような見方をすると、“おもて”の歌詞を次のように表記できます。 ふるさと求めては 内地もめ もめ もめは 内地もめ 勝って嬉しきは 内地もめ 負けて悔しきは 内地もめ 複数の内戦や、そのことで生じる米不足などに対する不満により起きた一揆で、国内がもめていることを表わした歌であると考えています。 --- 「はないちもんめ」にみられる「蛇行法則」が何を意味するのかと考えを巡らせ、「蛇行法則」は「惑星の逆行」を表わすのではないかと推察しました。惑星の逆行とは、天空における惑星の見掛け上の位置が、他の恒星に対して逆の方向へ移動しているように見える現象のことです。 この「惑星の逆行」の時期に、歌に表された「事象」が起きたのではないかと推察しました。 実際に、世直し一揆の中でも大規模な、武州世直し一揆が起きたのは、慶応二年六月(西暦1866年7月)ですが、その年の秋から冬にかけて、米価高騰が最高値に達した頃である、慶応二年十一月~同三年正月(西暦1866年12月頃~1867年2月頃)に、火星がふたご座で逆行しています。 冒頭の「準備が遅れ」とは、この、月日の「ずれ」を表していると考えています。 --- <参考図書> ・ 広辞苑 第五版 岩波書店 1998年 ・ 世界大百科事典 第2版 日立デジタル平凡社 1998年 ・ 上がる下がる―京のわらべうた 著者:吉川蕉仙 二玄社書店 2005年 ・ 近世国家の解体と近代 編者:津田秀夫 塙書房 1979年 ・ 日本史事典 .com https://nihonsi-jiten.com ・ 【換暦】暦変換ツール https://maechan.net/kanreki/ ・ Wikipedia ・ Stella Theater Pro Version2.66 Toxsoft 2008年 --- 戻る |